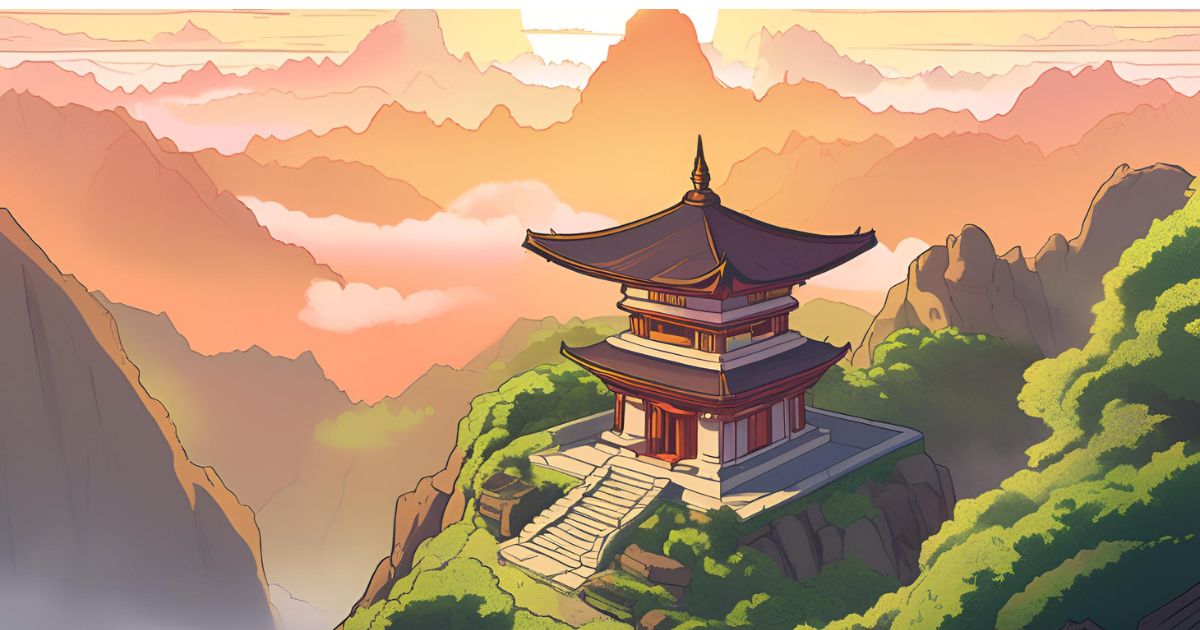静岡県島田市千葉にある千葉山智満寺で、毎年正月に行われる伝統行事「鬼払い」がおこなわれます。、赤、青、黄の三色の鬼を退治することで、一年間の無病息災のご利益が得られると言われるこの行事は、地域の人々に古くから親しまれてきました。
今回は、この独特な新年の祈願行事についてご紹介します
智満寺の鬼払い行事の由来
智満寺の鬼払いは、天正年間(1573-1592)から伝えられる奇祭です。
長い歴史を持つこの行事は、新年の厄除けと
無病息災を祈願する重要な儀式として、地域の文化に深く根付いています。
午後9時半頃から導師の読経が始まり、
堂内に集まった参拝者全員に厄除けが行われます。
午後10時半を越え、堂内の灯りが消され暗闇になると、
たいまつを持った三鬼が登場。
鬼は追い払われ堂外に逃げると、
持っていたたいまつを投げ捨てます。
このたいまつの燃えさしは、魔除けになると言われています。
集まった人たちは、次々に燃えさしに駆け寄り、
無病息災を願って自宅へ持ち帰っているそうです。
智満寺 奥之院と十本杉
智満寺の山頂には阿修羅坊さまが住み、
本尊千手観音さまの帰依者を守護すると云われています。
奥之院は、智満寺の山頂付近に位置する、
最も神聖な場所の一つです。
静寂に包まれたこの空間は、修行僧や参拝者にとって、
心を落ち着かせて祈りを捧げるための特別な場所となっています。
「十本杉」を含めてすべてが阿修羅坊さまの霊域でその中心となるお堂が奥之院です。
十本杉の名前
- 開山杉: 智満寺の開山である広智が植えたと伝えられるスギです。(今は倒木でなし)
- 大杉: 十本杉の中でも特に大きく、樹勢が旺盛なスギです。
- 達磨杉: 樹形が達磨大師に似ていることから名付けられました。
- 雷杉: 雷に打たれた跡が残っていることから名付けられました。
- 常胤杉: 源頼朝の家臣である常胤が植えたと伝えられています。
- 経師杉: 経典を書写する経師が植えたと伝えられています。
- 一本杉: 周囲の木々から離れて生えていることから名付けられました。
- 盛相杉: 樹形が力強く、堂々とした姿をしていることから名付けられました。
- 子持杉: 小さな木が根元から生えていることから名付けられました。(現在は枯死)
- 頼朝杉: 源頼朝が植えたと伝えられていましたが、現在は倒木しています。
鬼払いの流れ
鬼払いは以下のような流れで行われます:
- 夜9時過ぎに住職が入堂
- 万民豊楽・無病息災の祈願
- 参拝者全員への厄除けの法印加持
- 観音経の読誦
- 堂内の灯りが消され、鐘や太鼓の音が鳴り響く
- 暗闇に松明を持った三匹の鬼が現れ、堂内で暴れ回る
- 読経の法力によって鬼が追い払われる
三色の鬼の意味
赤、青、黄の三色の鬼は、それぞれ人間の煩悩を表しているとされます
- 赤鬼:むさぼりの心
- 青鬼:怒りの心
- 黄鬼:ねたみの心
これらの鬼を追い払うことで、人々の心から悪しき感情を取り除き、新年を清々しい気持ちで迎えることができると考えられています。
鬼払いのご利益
智満寺の鬼払いには、様々なご利益があると言われています
開運招福
- 智満寺は、参拝することで運を開き、福を目指す力があると信じられています。
商売繁盛
- 地元の商人や事業主たちが成功を祈願するために参拝する寺院です。商売における利益や良縁を祈りの場として大切にしています。
厄除け
- 智満寺は厄年や困難な時期を迎えた人々の厄除けを祈る場所でも有名です。
- 特に、厄払いのための祈祷や護摩供(ごまく)が行われます。
護摩供(ごまく)は護摩供養(ごまくよう)とも言い、
- 御本尊の前に設けた壇で火を焚き、祈りをささげる儀礼です。
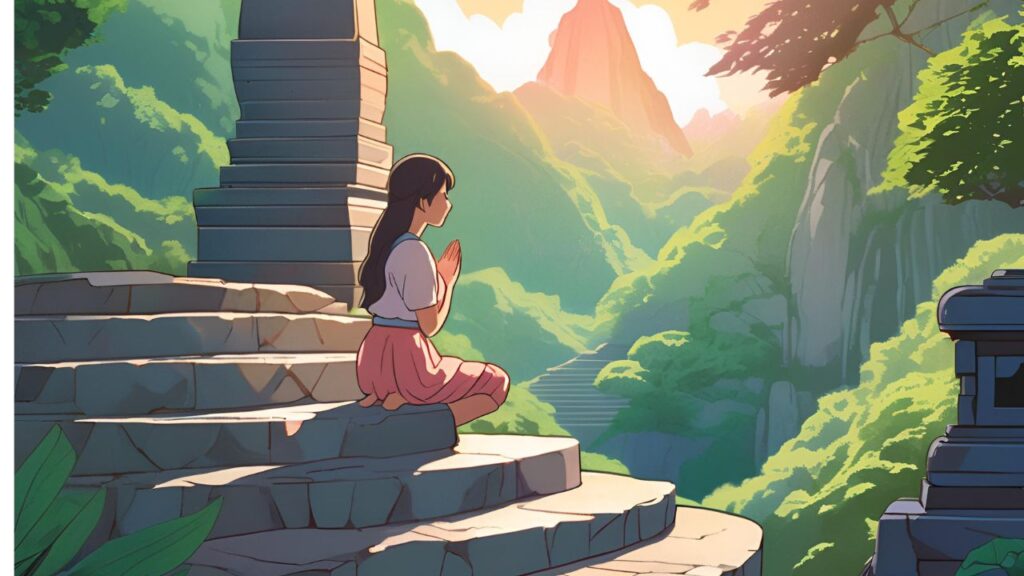
まとめ
千葉山智満寺の鬼払いは、新年の厄除けと無病息災を祈願する独特な行事です。
三色の鬼を退治することで煩悩を払い、清らかな心で新年を迎える意味が込められています。
地域の伝統文化として大切に受け継がれてきたこの行事は400年も受け継がれて、現代を生きる私たちにも、心の浄化と新たな出発の機会を与えてくれるのではないでしょうか。
アクセス
住所:〒427-0001 静岡県島田市千葉254
電話:0547-35-6819
公共交通機関でのアクセス方法や最寄り駅からの詳細な道順については、事前に確認することをおすすめします。
また、参拝の際は、寺院の規則やマナーを守り、静かで敬虔な態度で臨みましょう。